超ローコストPICWRITERの製作
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「PICBASICコンパイラ」からスピンオフ!!
過去記事を参照することなどを考えて該当する過去記事は「PICBASICコンパイラ」のまま連載回もそのままとします。
以後は前回記事からの流れで[第236回]からとします。
「PICBASICコンパイラ」はなるべく早く連載を再開したいと考えています。
PICはローコスト、高機能で種類も豊富なお手軽マイコンですがプログラムを書き込むためのWRITERが必要です。
それをできるだけ安価に作ってしまおうというプロジェクトです。
最終的には製品化を考えています(組立キット、完成品)。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
[第260回]
●PIC12F629(2)テストプログラム
いまさらですが、当記事はPIC WRITERの開発について書くのが主テーマです。
その主旨からすれば色々なPICをさわってその書き込みができればとりあえずの目的が達成されたことになります。
もうとにかく早く先に進めたいというのが本音であります。
しかし。
もうひとつ別の本音を言えば。
せっかく新規にさわることになったPICならばせめてとりあえずサンプルプログラムぐらいは書くべきではないか。
ただ書くだけではなくて、ちゃんと動作するプログラムを、です。
しかしながらそれはなかなかに面倒なことなのです。
なんたってPICはクセが強いのです。
余談でありますが。
なんですか。
インターネット上に散見されるPIC関連の記事を見ますと皆様大抵はPICのプログラムを書くのにCコンパイラをお使いのようで。
おいおい。
PICのプログラムをCで書くのかよ。
LEDチカチカなんてプログラムをCで書いたりして。
それで本当にその先に進むことができるの?
いささか首をかしげてしまいます。
PICはアセンブラでしょうよ。
いまどきはそう思うことがすでに化石人間の証なのかも。
今や絶滅危惧種でありましょう。
しかししかし。
あくまでわが道を行く。
ゴーイングマイウエイであります。
コンパイラなんてやったってちっとも面白くはありませんでしょう。
アセンブラはつまりはマシン語です。
直接CPUをダイレクトに動かせるのですよ。
それは8080でもそう、Z80もそう、ちょっと大変ですけれど8086だってそうです。
アセンブラならそういうプログラムが書けるのですけれど。
それはなかなかに習得が困難です。
その点PICは比較的アセンブラの習得が容易だと私は考えています。
アセンブラはニーモニックから1対1でマシン語コードに変換されます。
PICのアセンブラはちょいとクセツヨなのが困ったところではありますけれど。
なんたってたった35個の命令しかないのですから!
それも無理に全部覚える必要はありません。
わかるものから少しずつ使っていけばよいのです。
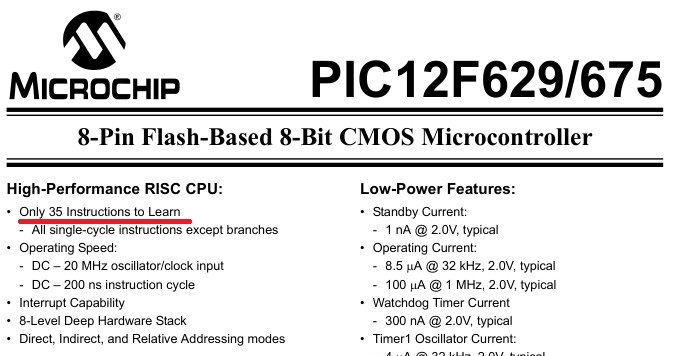
[出典]Microchip Technology Inc. PIC12F629/675 Data Sheet
これが全命令の一覧です。
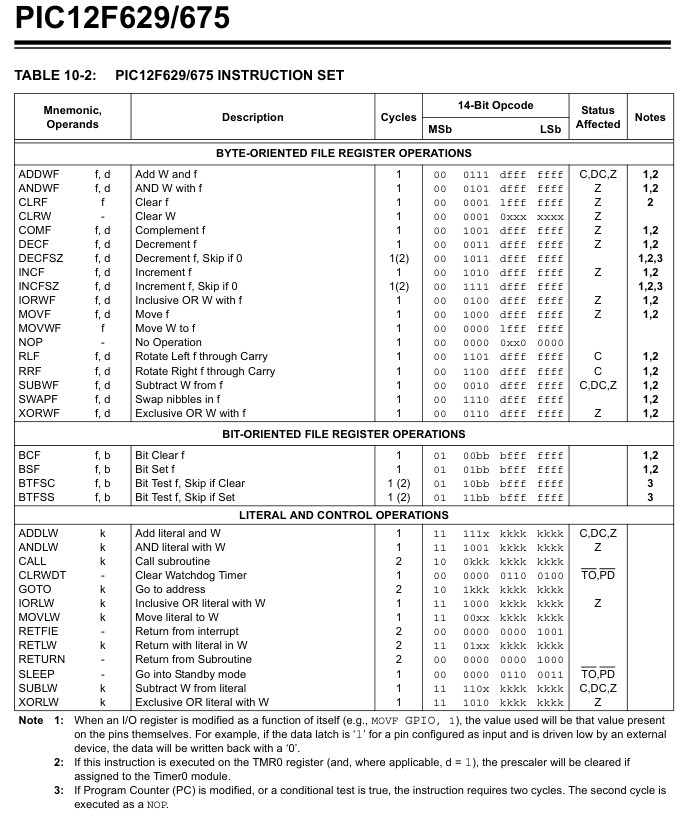
[出典]Microchip Technology Inc. PIC12F629/675 Data Sheet
たったこれだけです。
紙切れ1枚に収まってしまいます。
しかもこの命令の殆どが1命令クロック(1サイクル)で実行されます。
めっちゃ分かりやすいです。
1命令クロックは4CPUクロックです。
たとえばCPUクロックが4MHzの場合1命令クロックは1MHzつまり1μsで実行されます。
上の表でCyclesとあるのが命令クロックです。
CALL、RETURN、RETFIE、RETLW、GOTOのみが2サイクルです。
条件分岐命令(DECFSZ、INCFSZ、BTFSC、BTFSS)は条件により1または2サイクルです。
ね。
分かりやすいでしょう。
PICによってはこのほかに追加された命令を持つものもありますがそれは上級者になってからでよろしいでしょう。
あの。
上の表を見ておわかりでしょうか。
右の方14−Bit Opecodeというのがマシン語コードです。
嬉しいじゃありませんか。
ここまで書いてあります。
知的好奇心がしっかり満足させられます。
さらにさらに。
有り難いことにPICのData Sheetには命令の詳細まで説明されているのです!
下はその一部です。
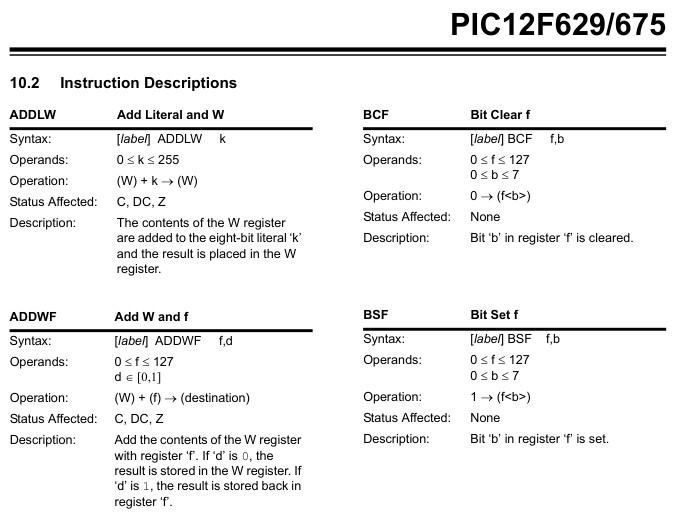
[出典]Microchip Technology Inc. PIC12F629/675 Data Sheet
ということで。
当連載記事では各PICごとに実際のテストプログラムを簡単なサンプルプログラムとしてそのリストを掲載するとともに実際にターゲットのPICに書いて実行して動作することを確認していきます。
もしもこれからPICをさわってみようとお考えでしたら、サンプルプログラムリストを参考にしてPICアセンブラプログラムの学習に役立ててください。
えっと。
私はアセンブラソースプログラムをアセンブルしてHEXファイルを作成するのに今はMPLAB IDEを使っておりますが。
それも主としてWindows98SE上で動くMPLAB IDE V8.40を使っています。
それで対応できないPICについてはWindows7上で動くMPLAB IDE V8.92を使っています。
MPLAB X IDEもダウンロードしましたがあんなクソなものは使えません。
そのうち自前のPICアセンブラを作ってしまうつもりでおります。
乞うご期待、であります。
前振りが長くなってしまいました。
PIC12F629のテストプログラムです。