乵戞侾俈俆夞乶
仠俶俢俉侽倅係俤偺夞楬恾偐傜丂俹俬俠偺岠梡
俶俢俉侽倅係俤偺夞楬恾偼乵戞侾俆俇夞乶偵偁傝傑偡丅
俶俢俉侽倅俁丏俆偺弶婜儌僨儖偲偟偰俶俢俉侽倅嘨慻棫僉僢僩傪惢嶌偟偰斕攧傪奐巒偟偨偺偼俀侽侾侾擭偱偟偨偐傜偦傟偐傜傕偆侾係擭傕宱偭偰偟傑偄傑偟偨乮乵戞侾侾侽夞乶乯丅
偙偺偙傠偼徚旓惻傕傑偩俆亾偩偭偨偺偱偡偹丅
壙奿偼俀俀侽侽侽墌乮惻暿乯偱偟偨偐傜偮偄愭擔傑偱偺俶俢俉侽倅俁丏俆慻棫僉僢僩偲摨偠壙奿偱偢偭偲傗偭偰偒偨偙偲偵側傝傑偡乮偦偺娫偵徚旓惻偼攞偺侾侽亾偵側傝傑偟偨乯丅
偦偺侾擭屻偵俶俢俉侽倅嘨傪儅僀僫乕僠僃儞僕偟俶俢俉侽倅俁丏俆偲偟偰斕攧傪奐巒偟傑偟偨丅
偦偺曄峏偼倅俛俁俢俷俽乮俠俹乛俵屳姺俢俷俽乯偵懳墳偡傞栚揑偱婎斅忋偵憹愝俼俙俵夞楬傪捛壛偟偨偙偲偱偡乮儚儞儃乕僪儅僀僐儞偱俠俹乛俵傪両乵戞俀俁俈夞乶乯丅
廫擭傂偲愄偲偄偄傑偡偐傜傂偲愄傪墇偊偰偢偭偲摨偠壙奿偱傗偭偰偒偨偙偲偵側傝傑偡丅
偦偺娫偵僷乕僣偺巇擖壙奿傕彮偟偢偮忋偑傝偙偲偵嬤擭偺墌埨傕偁偭偰偝偡偑偵偙偺傑傑偱偼柍棟偲偄偆偲偙傠傑偱棃偰偟傑偄傑偟偨丅
偦傟偱傗傓傪摼偢愭擔俶俢俉侽倅俁丏俆慻棫僉僢僩偍傛傃姰惉昳偺抣忋偘偵摜傒愗傝傑偟偨丅
偙偲偼俶俢俉侽倅俁丏俆偩偗偱偼側偔偰偦偺傎偐偺傎傏慡惢昳偵媦傃傑偡丅
帪娫傪傒偮偗偰彮偟偢偮尨壙寁嶼傪偟捈偟側偑傜壙奿偺夵掕傪偟偰偄偔梊掕偱偡丅
偟偐偟偨偩扨偵尨壙偑忋偑偭偨偐傜抣忋偘傪偡傞偲偄偆偺傕側傫偩偐側偁偲偄偆姶偠偱偡偟侾侽擭埲忋傕摨偠夞楬偺傑傑傗偭偰偒偰偄傞偙偲偱偡偐傜偙偙傜偱壗偲偐堦岺晇偱偒側偄傕偺偐偲柍偄抦宐傪偟傏偭偨寢壥抋惗偟偨偺偑俶俢俉侽倅係俤偱偡丅
俤偼俤們倧値倧倣倷偺堄偱偡丅
昁梫惈偑掅偄偲巚偆夞楬偼巚偄愗偭偰徣偔偙偲偵偟傑偟偨丅
偄傑偳偒俼俽俀俁俀俠傕柍偄偩傠偆偲偄偆偙偲偱徣偒傑偟偨丅
俼俙俵偺儊儌儕僶僢傾僢僾傕俽俙倁俤乛俴俷俙俢偺婡擻傪巊偊偽徣偔偙偲偑壜擻偲峫偊偰徣偄偨寢壥儊儌儕廃傝傕偡偭偒傝偟傑偟偨丅
俶俢俉侽倅俁丏俆偱偼俉俀俠俆俆偺慡億乕僩傪儐乕僓乕偵奐曻偡傞偨傔偵俿俲亅俉侽偱偼僉乕僗僀僢僠偺傾僋僙僗偵俉俀俆俆傪巊偭偰偄偨偲偙傠傪俈係俫俠儘僕僢僋俬俠偱戙梡偟偰偄傑偟偨丅
偙偙傕俿俲亅俉侽偵栠偭偰俉俀俠俆俆偱僉乕僗僀僢僠偵傾僋僙僗偡傞傛偆偵夵傔傑偟偨丅
傕偭偲傕戝暆偵夞楬傪曄峏偟偨偺偑俈僙僌儊儞僩俴俤俢昞帵夞楬偱偡丅
壓偼俶俢俉侽倅俁丏俆偺俴俤俢昞帵夞楬偱偡丅
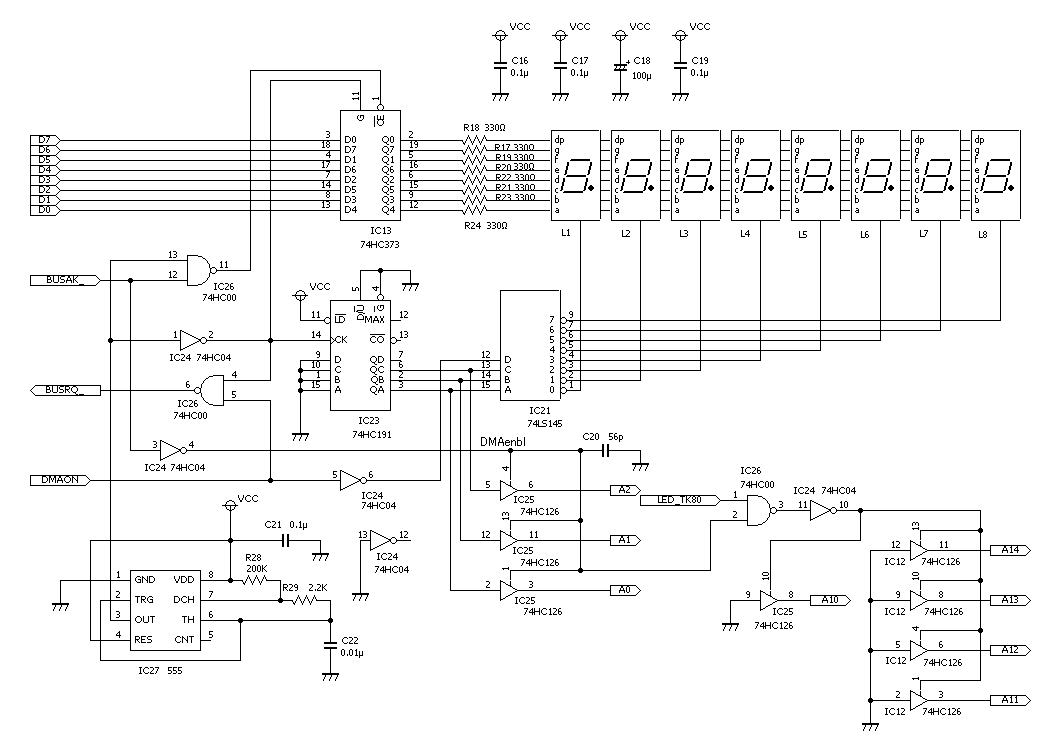
摦嶌偲偟偰偼俿俲亅俉侽偲摨偠俢俵俙夞楬偵側偭偰偄傑偡丅
僞僀儅乕俬俠俆俆俆偵傛偭偰廃婜僷儖僗傪俠俹倀偵憲傝抁偄帪娫俠俹倀偺摦嶌傪掆巭偟偰傾僪儗僗僶僗丄僨乕僞僶僗偲儊儌儕偺傾僋僙僗怣崋傪奐曻偝偣偰俼俙俵偺俴俤俢昞帵僨乕僞偑偁傞傾僪儗僗傪弴偵撉傫偱偦偺僨乕僞傪俈僙僌儊儞僩俴俤俢偵昞帵偝偣偰偄傑偡丅
俈係俫俠侾俋侾偼俴俤俢偺昞帵寘傪慖戰偡傞偨傔偺僇僂儞僞偱俈係俫俠俁俈俁偼俼俙俵偐傜撉傒弌偟偨昞帵寘偵懳墳偡傞抣傪昞帵婜娫拞儔僢僠偟偰偍偔偨傔偵巊偭偰偄傑偡丅
俈僙僌儊儞僩俴俤俢偼僟僀僫儈僢僋揰摂傪峴側偭偰偄傑偡丅
慡寘傪忢帪揰摂偝偣傞偺偱偼側偔偰悢昐俫倸偱抁帪娫偵堦搙偵侾寘偩偗傪弴偵揰摂偡傞偙偲偱恖娫偺栚偵偼慡寘偑揰摂偟偰尒偊傞昞帵曽幃偱偡丅
奺寘偺昞帵偼傢偢偐側婜娫昞帵偡傞偩偗側偺偱昞帵偡傞婜娫偼戝偒側揹棳傪棳偟偰柧傞偔岝傜偣傑偡丅
偦偺偨傔奺俴俤俢偺僐儌儞抂巕偵偼慡僙僌儊儞僩偺揰摂帪偵偼抁帪娫偱偡偑偐側傝戝偒側揹棳偑棳傟傑偡丅
偦偺抣偼昗弨揑側俈係俫俠儘僕僢僋偺嫋梕抣傪墇偊傑偡偐傜俴俤俢僪儔僀僽偺偨傔偵俈係俴俽侾係俆傪巊偭偰偄傑偡丅
偄偢傟偺俬俠傕壙奿偑崅偔側傞偲偲傕偵擖庤偑崲擄偵側偭偰偒偰偄傑偡丅
摿偵俴俽侾係俆偼怺崗偱偡丅
幚偼俶俢俉侽倅俁丏俆偺俈僙僌儊儞僩俴俤俢昞帵夞楬偼俿俲亅俉侽傛傝傕暋嶨偵側偭偰偄傑偡丅
塃壓偺俙侾侽乣俙侾係偵偮側偑傞夞楬偼俿俲亅俉侽偵偼柍偄夞楬偱偡丅
俿俲亅俉侽偼彫偝側儊儌儕梕検偺俼俙俵傪搵嵹偟偰偄偨偺偱俈僙僌儊儞僩俴俤俢偺昞帵傾僪儗僗偼俉俁俥倃偵偁傝傑偟偨丅
俶俢俉侽倅俁丏俆偱偼俇俀俀俆俇宆偺俁俀俲俛偺俼俙俵傪搵嵹偟偰偄傑偡偐傜俼俙俵偺傾僪儗僗偼俉侽侽侽乣俥俥俥俥偵側傝傑偡丅
塃壓偺夞楬偑柍偄偲俈僙僌儊儞僩昞帵僨乕僞偺傾僪儗僗偼俥俥俥倃偵側偭偰偟傑偄傑偡丅
俶俢俉侽倅儌僯僞僾儘僌儔儉偱偼偦偺傛偆偵側偭偰偄傞偺偱偡偑愄偺俿俲亅俉侽偺僾儘僌儔儉傪憱傜偣傛偆偲偡傞偲俈僙僌儊儞僩俴俤俢偵昞帵偱偒傑偣傫丅
俶俢俉侽倅俁丏俆偺僔僗僥儉俼俷俵偵偼俶俢俉侽倅儌僯僞僾儘僌儔儉偲俿俲亅俉侽儌僯僞僾儘僌儔儉偑擖偭偰偄偰僗僀僢僠偱慖戰偡傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅
塃壓偺夞楬偼俿俲亅俉侽儌僯僞僾儘僌儔儉偑慖戰偝傟偰偄偨傜傾僪儗僗偺俙侾侽乣俙侾係傪嫮惂揑偵侽偵偡傞偙偲偱俉俁俥倃偑慖戰偝傟傞傛偆偵偡傞偨傔偺傕偺偱偡丅
偦偺晹暘傪娷傔偰慡懱偲偟偰偐側傝懡偔偺儘僕僢僋俬俠傪巊偭偰偄傞偺偱僐僗僩掅尭偺偨傔偵偼偙偙偼堦斣側傫偲偐偟偨偄偲偙傠偱偟偨丅
幚偺偲偙傠嵟戝偺僐僗僩崅偺梫場偼僉乕僗僀僢僠偺崅摣偱偟偨丅
側偐側偐偵偟偭偐傝偟偨僉乕僗僀僢僠側偺偱偡偑巇擖傟偺搙偵壙奿偑忋偑偭偰崱偱偼愄偺悢攞偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅
偙傟偑堦斣偺僐僗僩傾僢僾梫場偱偟偨偺偱俶俢俉侽倅係俤偱偼斾妑揑掅壙奿偱擖庤偱偒傞僞僋僩僗僀僢僠偵曄峏偟傑偟偨丅
榖偑偦傟偰偟傑偄傑偟偨偑僉乕僗僀僢僠偵師偄偱側傫偲偐偟偨偄偲巚偭偨偺偑忋婰偺俈僙僌儊儞僩昞帵夞楬偱偟偨丅
偱丅
夞楬恾傪挱傔偰偄偰巚偄偮偄偨偺偑偙偺夞楬傪俹俬俠偵抲偒姺偊弌棃側偄偐偲偄偆峫偊偱偟偨丅
崱偼彮偟偍媥傒偟偰偄傑偡偑偮偄偙偺娫傑偱俹俬俠俛俽僐儞僷僀儔偲偐俹俬俠倂俼俬俿俤俼偲偐偱寢峔俹俬俠傪偄偠偔偭偰偄偨偠傖偁傝傑偣傫偐丅
崱偙偦丅
偙偙偵俹俬俠傪巊偆傋偒丅
偑偟偐偟丅
俠俹倀夞楬偵俹俬俠傪巊偍偆偲偡傞偲偒偵忈奞偲側傞偺偼俹俬俠偑抶偄偲偄偆偙偲偱偡丅
壗傪尵偭偰傞偺丅
俶俢俉侽倅俁丏俆偺俠俹倀僋儘僢僋偼俇俵俫倸偩偗偳偄傑偳偒偺俹俬俠側傜晛捠偵俀侽俵俫倸偼偄偗傞偱偟傚偆丅
偦偆側偺偱偡偗傟偳丅
偦偺掱搙偺僋儘僢僋偱偼俠俹倀偺廃曈俴俽俬偲偟偰偼偲偰傕巊偊側偄偺偱偡丅
寁嶼傪娙扨偵偡傞偨傔偵倅俉侽偺僋儘僢僋偑係俵俫倸偩偭偨偲偟偰俬俷倂俼怣崋偺僷儖僗暆偼傢偢偐侽丏俆兪倱偟偐偁傝傑偣傫丅
堦曽偱俹俬俠偼俀侽俵俫倸偺偲偒侾柦椷傪侽丏俀兪倱偐侽丏係兪倱偱幚峴偟傑偡偑偦傟偱偼俠俹倀偐傜弌偝傟傞倂俼怣崋傪尒偰壗傜偐偺張棟傪偡傞偙偲偼偲偰傕偱偒傑偣傫丅
妱崬傒傪巊偭偨偲偟偰傕柍棟偱偡丅
俠俹倀僶僗怣崋偵崌傢偣傜傟傞傛偆側婡擻偺俹俬俠傕偁傞傛偆偱偡偑扨弮側俹俹俬乮俹倰倧倗倰倎倣倣倎倐倢倕丂俹倕倰倝倫倛倕倰倎倢丂俬値倲倕倰倖倎們倕乯偲偟偰巊偆側傜偲傕偐偔偲偟偰崱巊偄偨偄偲巚偭偰偄傞傛偆側偪傚偄偲暋嶨側夞楬偺抲偒姺偊偵偼偲偰傕巊偊傑偣傫丅
傗偭傁傝側偁丅
柍棟偩傛側偁丅
堦扷偼掹傔傛偆偲偟偨偺偱偡偗傟偳丅
偦偙傪傕偆傂偲婃挘傝丅
夞楬恾傪偆乕傫偲偆側偭偰尒媗傔偰偄傑偟偨傜丅
傗偭偲婥偑晅偒傑偟偨丅
偁傟丠
偦偆偩偭偨丅
偙偺夞楬丄俢俵俙偠傖偁傝傑偣傫偐丅
偮偆偙偲偼丅
僋儘僢僋偑抶偔偰傕偲偵偐偔尒偨栚晄帺慠偵側傜側偄掱搙偺懍搙偱僟僀僫儈僢僋揰摂偑偱偒傟偽偄偄両
偦傟側傜偱偒傞偠傖偁傝傑偣傫偐丅
偲偄偆偙偲偵婥偑偮偄偰俹俬俠偵抲偒姺偊偨偺偑壓偺夞楬偱偡丅
偙偺夞楬恾偼乵戞侾俆俇夞乶偱偍尒偣偟傑偟偨丅
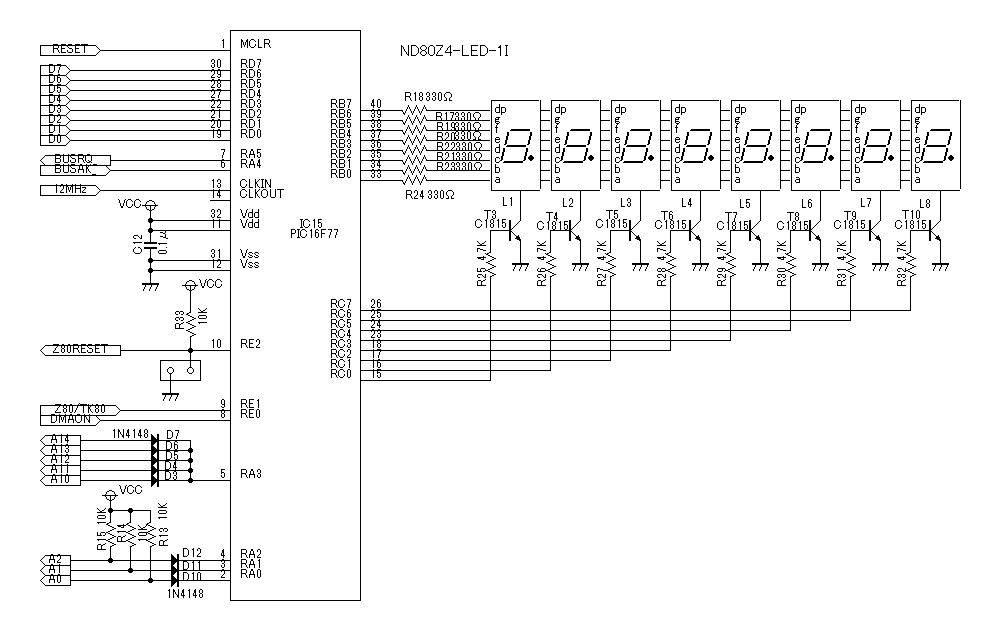
俶俢俉侽倅俁丏俆偺俈僙僌儊儞僩俴俤俢昞帵夞楬傪俹俬俠侾屄偱抲偒姺偊偰偟傑偄傑偟偨丅
側偍俹俬俠偺億乕僩弌椡偱傕俈僙僌儊儞僩俴俤俢偺僟僀僫儈僢僋揰摂傪僟僀儗僋僩偵峴側偆偺偼彮偟偒偮偄偺偱僩儔儞僕僗僞偱僪儔僀僽偟偰偄傑偡丅
偙偙偼俈係俴俽侾係俆偺抲偒姺偊偱偡丅
儚儞儃乕僪儅僀僐儞傪偮偔傠偆両乵戞侾俈俆夞乶
俀侽俀俆丏侾侽丏俁侾倳倫倢倧倎倓
慜傊
師傊
儂乕儉儁乕僕僩僢僾傊栠傞